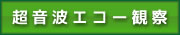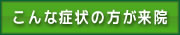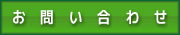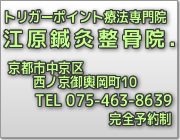最新の記事
- 2025年05月26日(月)
Rexトリガーポイント研究会・施術用ツールを追加しました。 - 2025年02月06日(木)
日本は痛み医療の最貧国? - 2025年02月03日(月)
あなたの痛みは画像検査ではわからない? - 2024年12月06日(金)
痛みを感じる仕組み自体に変調を起こす痛み - 2024年11月15日(金)
現役整形外科医のブログより
月別アーカイブ
治療室日記 (2013年04月)
痛みに関する話題を綴った日記です。
私の鍼治療は、機能不全の状態にある筋肉を出来るだけ再生させるイメージで行っています。
機能不全になった筋肉とは、一言で言えばうまく伸び縮みできない状態です。それを筋硬結と言います。
初期のトリガーポイント鍼の考え方は、筋硬結の周囲に出来たトリガーポイントがターゲットのようでした。
筋が伸びるには、酸素(O2)とアデノシン三リン酸(ATP)が必要になります。
筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)は、筋の病変ですから、病変を回復しなければ治療効果は長持ちしないように感じます。
そう考えれば、計画的に機能不全に陥った筋肉に傷を付けることは、理にかなっています。
傷を付けると言うと、痛いイメージを持たれるかもしれませんが、気持ちいい~と仰る方が殆どですから、痛いと言うことではありません。
この感覚は、他の言葉で表現することが出来ないのが残念です。
ビニール紐を広げた状態=筋線維が固まって、うまく動けない状態の筋硬結のイメージ。
.jpg)
トリガーポイント鍼で、筋の塊が解けて機能を取り戻したイメージ。

カテゴリ:鍼灸
ebara / 2013年04月19日(金) 08:05
トリガーポイント鍼の特徴に感作構造(痛みの原因となる場所)を壊すという考え方があります。
痛みをその場で取るだけでなく、痛みの構造を根っこから抜くのですから、効果が長持ちします。
先日、屈強なスポーツ選手が、競技中に痛めた足首を診せに来院くださいました。
実は、この患者さんは、学生時代から、慢性化した酷い腰痛持ちでした。
就職してから更に悪化して、知り合いの紹介で来院くださったのが始まりです。
この患者さんには、二回施術をしています。最近、腰の調子はどうですか?とお尋ねすると、下記のようにお話しして下さいました。
そう言われれば、最近、腰が気になりませんね~
すっかり、腰痛持ちだったことを忘れていました。(笑)
こういう回復の仕方は、治療のインパクトが弱いですね。(笑)
鍼灸は、わざと組織に傷を付け、その傷が治る際に、感作構造(悪いところ)も潰れてしまうことを期待します。
余計な部分を傷つけないように、罹患筋の推定⇒触診⇒鍼を打つ技術が重要になります。
筋の細胞が入れ替わるまでに、三カ月とも言われますから、トリガーポイント鍼の本当の効果は、治療直後よりも、数ヵ月後に遅れてやって来るのかもしれません。

カテゴリ:鍼灸
ebara / 2013年04月17日(水) 18:33
立ち仕事で力仕事も多くいつも体の凝りから痛みを感じていました。自律神経失調症や慢性疲労の症状も持っているので、ひどい時はめまいのような症状がありましたが、週に1回程度トリガーポイント治療を受けるようになってから痛みも楽になり元気に仕事ができるようになりました!
最近では突然首が動かなくなって針治療をしてもらったら翌日には首が動くようになって驚きでした。

トリガーポイント療法専門院の江原鍼灸整骨院.は、上記のような痛みや症状以外にも、筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)、筋痛症の患者様が多数来院される治療院です。
・痛みの体験記
・ブログを書く理由
・こんな症状の方が来院
・トリガーポイント療法専門院の江原鍼灸整骨院.ホームページ
・京都市中京区西ノ京御輿岡町10番地
(JR円町駅を北へ徒歩5分。島津アリーナ京都を南へ100メートル。)
円町、大将軍、白梅町、等持院、花園、西ノ京、太秦、鳴滝、宇多野、御室方面からもすぐです。
・診療時間 9:00~19:30(水・土 午前中のみ)
・定休日 日曜日 祭日
・電話 075-463-8639
・「ホームページをみて…」とお電話ください
メールでのお問い合わせ⇒メールフォーム
カテゴリ:患者様の声
ebara / 2013年04月17日(水) 09:01
私は、ギックリ腰をくり返していて、今まで3回くらいほどありました。その都度、安静にしていれば治っていました。
そんななか、仕事をはじめてから4年目、背中の張りから腰の痛み、いつもとは違う感じでしたが、なんとか仕事は続けました。
しかし、ある日またギックリ腰になり、いつも通リ整体に行きました。
少しはましになるのですが、張り感が全くとれませんでした。
痛みは増すばかりで、ギックリ腰から六ヶ月後、左側にしびれが出たので整形外科に行くと、椎間板ヘルニアだと診断されました。
手術するほどの椎間板ヘルニアではないので、痛み止めですごしましょうということでした。
しかし、ブロック注射は効かず、ただ、頭痛が残るのみでした。次にペインクリニックをすすめられましたが、その薬も副作用が強く飲み続けられませんでした。
こうなるともう、どうしていいのかわからず、精神的に疲れ人と接する事が苦になり、家にこもっていました。
そんな生活が4ケ月ほど続いた日、主人がインターネットで江原鍼灸整骨院.があることを知り、トリガーポイント鍼治療を受けてみました。
最初は、一進一退でしたが、続けて通うちに、自分が以前より行動できている事に気付きました。
そうなると、気持ち的にも楽になり、家にこもらなくらりました。今も、通っていますが、体が楽になっているのが確実に実感できています。
また、先生ご自身が痛みを体験されており、共感していただけることも信頼できる大きな要因でした。
痛みに対して、後ろ向きだった時、先生にお会いしていくうちに、前向きになり、痛みと向き合えるようになりました。
今後もゆっくりですが前進していこうと思います。
.jpg)
カテゴリ:患者様の声
ebara / 2013年04月06日(土) 14:12
http://www.jsccnet.org/12_conf/12_conf_intervew_kumazawa.html
今日から新年度のスタートです。このブログでは、上記の記事を何度も紹介していますが、生きている限りどこかしらで痛みに苦しめられる時期があると思います。その時に備えると言う意味、自分の備忘録として、記事を抜粋させていただきます。
抜粋スタート
痛覚受容器が興奮して、それが脳に伝わってどこが痛むのかを感ずる。独立した神経系であるということが明らかになったわけです。ところが末梢の痛覚受容器を介さない、つまり、末梢に傷がなくても、傷が治っていても痛いことがある。幻肢痛を考えればよく分かると思いますが、そういう痛みは正常の痛覚受容器を介して発生する痛みの機序では説明できない。
中略
覚えておいていただきたいことは、生理的に備えられた警告信号としての痛み、つまり生理的な痛みは「症状」としての痛みですが、中枢で可塑的な変化が出来上がってしまって末梢の痛覚受容器を介さないでも起こる痛みもあること。そして、こういう痛みは身体のどこかに傷があることを知らせる症状ではなく、新しく出来上がった「病気」だということです。
中略
痛みは痛覚神経、触覚は触覚神経と、一応そういう風に分かれているのが常識的な理解で、分けて考えるのは当たり前なわけです。だから、触覚で痛みが出るのはけしからんことで、前にも言いましたが、詐病やら心因性やらを疑われていました。 神経系の混線という生物的な変化が可塑的に出来上がって、変な系と繋がっちゃったために、その別の系の性質が入ってくるという可能性が示唆されたわけです。興奮が神経全ての伝達の根源ですから、別の性質のニューロンと混線をすれば、痛覚刺激でない興奮も痛みとなりうる。だから、自律神経系と混線すれば、お天気によって痛みが起こることも理解できるようになりました。そういうことが分かってきてガラッと変わったんですよね。何でも起こりうるということです。
「そういうことが本当に起こるんだ」ということになれば、今までに理解できなかった痛みも「あり得る」という理解になり、新たな発見だった。臨床家はそういう患者の訴えがあったら、それをまともに受け止めるべきです。それが痛みというものだと。極端なことを言えば、患者が痛いと言えば痛いんだと。そう思わねばならないですね。
中略
末梢神経で傷を受けると、シュワン細胞という神経を取り囲む細胞が免疫系の細胞なので、それが刺激を受けてサイトカインとかグルタミン受容体などの新しい発現(expression)を起こします。そして中枢にも影響を及ぼすようになり、今までの脳の正常な機能の結びつきが歪んでくるのです。脳の可塑性が意外に簡単に起こるということなのです。それが臨床の一例一例で、どの系がどうなって、どの受容器が感作されているとか、そういうことは分からないのだけれども、そういう神経系の中での変化がそのまま残ってしまうようなものを可塑性と言うんですね。形を変えて神経系にそのまま大きな顔して残っちゃうんです。そういう可塑性が痛みを引き起こす可能性が分かってきた。そうなると、痛みの治療というものが全く違ってくるわけですね。
中略
痛みとくれば「どこかに傷害があるだろう」と考えるわけです。傷害があれば、「それを感じる痛覚受容器が働いている」と思って、やたらに神経ブロックをしたり、オピオイドも急性痛や癌などの痛みに効きやすいので使ったりする。ところが効かないわけです。長期間にわたって効果のない治療をやって医療費のものすごい無駄使いしているわけですよ。全然違った原因で起こる痛みを、見当外れなところで対応しているのです。 今まで医者が持っていたテクニックは、例えば急性痛は効くような消炎鎮痛剤とかオピオイドですね。そういうものを使って効かない症状が出てきたら、医者はもう立ち往生なんですね。で、手術でそういう部分を切り取っても、「痛みがとれない、どうしよう」となるわけです。
中略
もう一つの防御機構としては、前にも言いましたが、防御姿勢をとることがあげられます。慢性痛症においても、痛みがあれば人間は必ずそれを防御する姿勢をとる。慢性痛症の場合は末梢に原因がない痛みですが、痛みを感じる部位は存在していて、それをプロテクトする。変な姿勢を何週間も続けていれば、健常な人でも痛みが起こりますよね。つまり、防御姿勢をとり続けるがために末梢組織に2次的な障害を起こして急性痛が発生してしまう。こういう経過で慢性痛症の痛みと2次的に発生した急性痛とが混在しているわけです。
中略
その2次的な痛み、そういう痛みを取り除くだけで、かなりの患者さんが痛みから逃れられる。
防御姿勢などによって増幅された痛みを取り除いてから、次に、慢性痛症の痛みを真っ当に慢性痛症として治療してもらう。慢性痛症の治療にあたっては、神経系の混線が問題なのですからあらゆることとの繋がりを考えねばなりません。意識のレベル、記憶のレベル、その人の人生の歴史から何から全てが絡み合って歪んで、可塑的に変容してしまって、どこかに痛みが発生するわけです。
それをいろんなフィールドからみて、それに対処する。正常な働き(habilitus)に戻す(re)ことをリハビリテーション(rehabilitation)と言います。可塑的に変化してしまったものを再びハビリテートする。そういう努力がいるのですが、そのためには2次的に起こった痛みが先ず取り除かれてからリハビリがスタートするのであって、それを取り除かないうちは手が付かないはずなんですけれども、従来の医療はその原則的な流れを無視してやってきた。それで患者としては「いくら治療しても少しも変らない」「他にいい所があるかもしれない」とドクターショッピングする。だから、そこの時点できちんと鑑別してもらえば、痛みそのものは治せない場合があるのですが、そういう痛みの成り立ちが分かれば、これは患者にとってはすごく安心なんですね。ある程度の痛みの軽減を作ってあげて、残った痛みを「それならばそれで付き合っていこうか」というレベルまで持って行くのが現在の治療法です。まだ慢性痛症に特効する薬は開発されていませんから、2次的に起こった痛みを取り除いて、患者さんの活動性を上げることが痛みの軽減に繋がっていくわけです。
抜粋終わり
.bmp)
カテゴリ:痛み痺れ
ebara / 2013年04月01日(月) 08:40